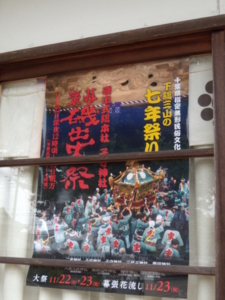祭神 建速素盞嗚尊・奇稲田姫命・大己貴尊
七年祭での役割 子守り
262-0032 千葉市花見川区幕張町2-989
→ 下総三山の七年祭り 湯立祭(小祭)
→ 「下総三山の七年祭り」関連の記事
五連休初日の今日は土曜日。
いつもであれば迷わず土曜眉二郎なんですが、
四日連続ラーメン、二日連続二郎となる為、
かみさんに強くたしなめられて、
あくまで自発的に今日は「自粛」と致します。(泣)
さて長男の顔に出来て悪化したアレルギー性湿疹。
幕張本郷の皮膚科に診てもらうことになりました。
眉二郎開店15分前、車で店の前を通過すると、
行列にはしろさんと黒烏龍茶さんが、
楽しそうに談笑しています。
嗚呼、おいらもその後ろに並びたいっ!!。(笑)
後ろ髪を引き抜かれながら、
後頭部に風を感じ
涙で咽ぶ私は、幕張本郷に向かいます。(汗)
名医と評判の皮膚科です。
なんと、待ち時間は二時間以上ということなので、
診察券を出して、携帯電話のi-modeで待ち時間をチェックしながら、
どこかで暇つぶしをしようということになりました。
そうそう幕張には「下総三山の七年祭り」での、
幕張磯出大祭(磯出式)での磯出式総本社をつとめる、
子守神社がありましたっけ。
磯出式とは大祭の夜中から次の日の朝にかけて、
二宮神社(父・夫)と子安神社(母・妻)、
三代王神社(産婆)とこの子守神社(子守り)の四社のみが、
幕張の浜辺に出て安産を祈願するという儀式です。
子守神社、私はお参りしたことがありません。
・・・早速伺ってみました。
昔は浜辺のすぐ手前だったという旧千葉街道から、
細い路地を北に入ると、
この平成に建てられた石造の鳥居があります。
鳥居を車でそのままくぐると左手に参拝者用の駐車場。
さすがに幕張磯出大祭(磯出式)の専門のポスターがありました。
磯出式、一度は見てみたいとも思いますが、
六年に一度の深夜早朝の祭事ですから、
なかなかその機会がありません。
しかし、埋め立てで、この神社からも、
海は遠く遠くなってしまったものです。
まだ真新しい拝殿です。
最近改築されたのでしょうか。
境内拝殿正面左側には、
樹齢推定200〜250年とされるご神木の大銀杏があります。
短い樹齢の割には太く雄雄しい立派な大樹です。
さて、こちらのご由緒です。
この神社自体の創建は不明ですが、
一番古い記録はやはり千葉氏にあります。
千葉介平常胤の四男、大須賀四郎胤信は、
父からこの幕張の地を譲り受けて城を築きました。
建久四年(1194)源頼朝の命でお狩場に赴く前に、
この神社に祈願するといい成果が得られたとかで、
その御礼で社殿を造営しました。
当初は馬加城近くにあったそうですが、
おそらく漁場の移動した氏子とともに、
現在のこの地に遷座したようです。
表記名がちょっと違いますが、
父であり夫である二宮神社と、
ご祭神がほぼ同様です。
やはり主祭神はスサノオで、
こちらは当初「素加天王神社」とされていたよう。
馬加城の「馬加」も、
磯出式の祭馬の様子ともされ、
一時は「馬加神社」とも称されたそうですが、
結局七年祭の役割そのものが、
現在の「子守神社」となって落ち着いたようです。
社殿提灯他にも、
多く掲げられている紋は「九曜に月星」。
まさに千葉氏の神社です。
拝殿左側奥から、裏の本殿を除き見ると、
なんてご丁寧なことにガラス張りのシースルー。
本殿は彫刻が素晴らしい歴史のある古い建物がみえました。
境内末社には、この池のある厳島神社や、
他の石碑群と一緒になってあった石の小祠の稲荷社。
そして仮の社務所のようなプレハブの中に、
なぜか天神社がひっそりと祀られています。
おやっ、この忠魂碑は、
大正五年(1916)に、
後の陸軍大将で総理大臣にもなった、
田中義一氏が陸軍中将時代に書したもの。
力石は珍しくありませんが、
これはかなり大きい方に分類されるね。
無銘ですが、おさらく軽く100kg以上あるでしょう。
これを昔の小さな人が持ち上げたって聞くと、
やっぱり驚いてしまいますけど、
幕末当時は米俵をもったまま宙返りしたお相撲さんもいたそうで・・・。
・・・・・・ほんまかいな。
![]() ← 二つのブログランキングに参加しております。
← 二つのブログランキングに参加しております。
 ← よろしかったら応援クリックをお願い致します。
← よろしかったら応援クリックをお願い致します。